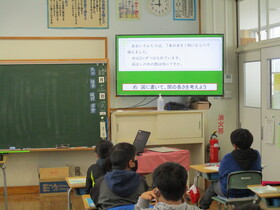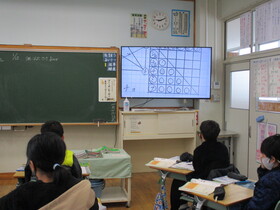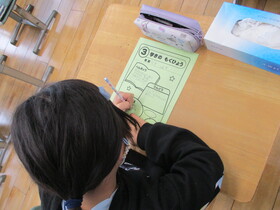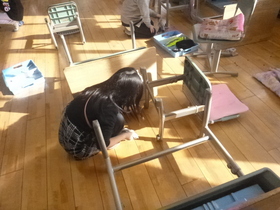本県にも本日、1月14日から2月7日までの緊急事態宣言が出されました。新規感染報告が過去最多を記録し続け、医療体制がひっ迫しています。この現状に歯止めをかけ、減少傾向に転じさせることが目的です。
それに伴い、学校における感染症対策として、文書を発出いたしました。下記のリンクを見ていただくか、左記の「お知らせ」-「新型コロナウイルス感染症に関わる内容」-「児童の感染症対策について」をご覧ください。ご協力をお願いいたします。
https://www.town.taka.lg.jp/sugisyou/news/contents_type=885
 多可町立杉原谷小学校
多可町立杉原谷小学校